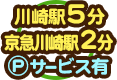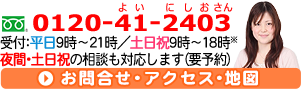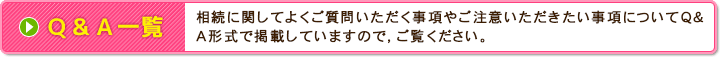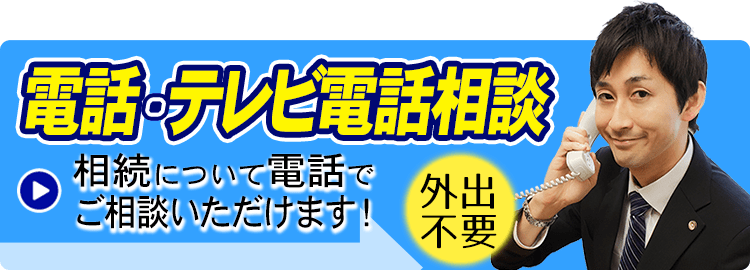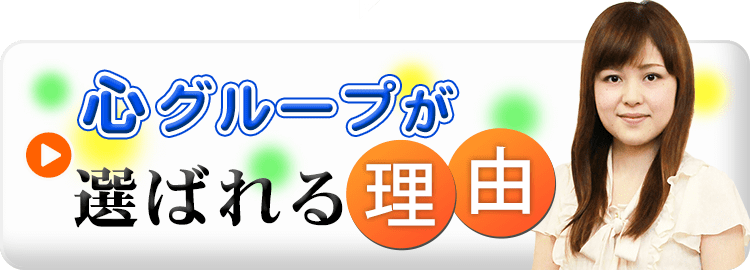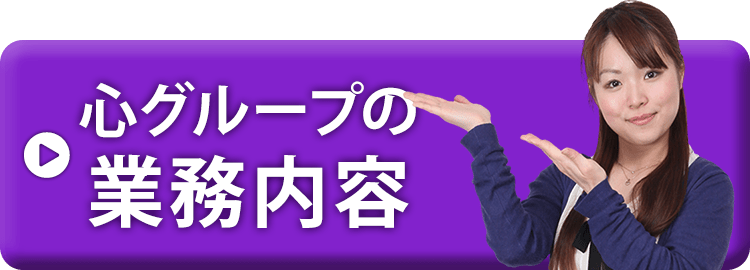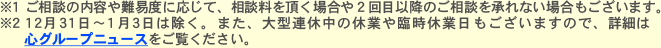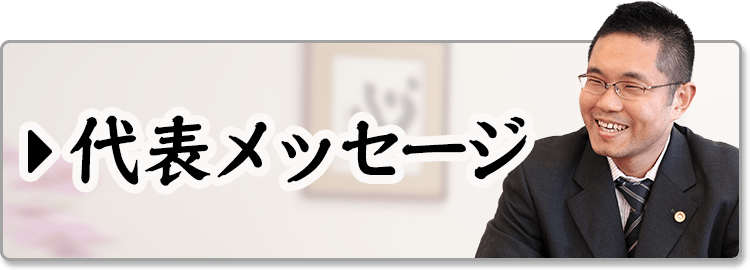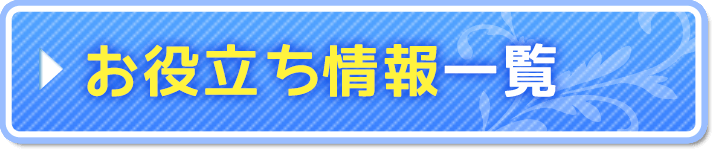亡くなった人の預金が少額の場合でも相続手続きは必要か
1 亡くなった人の預金が少額の場合、放置しても大丈夫か?
亡くなった方の預金を相続したら、相続手続きが必要です。
通常、口座の名義人が亡くなると、その口座は凍結されますので、相続手続きをしないと、口座から預金を引き出すことができないためです。
しかしながら、口座にある金額が少額であったり、預金がないという場合、特にお金を引き出す予定がないのでそのままにしているという方も多いのではないでしょうか。
預貯金については、相続手続きが義務化されておらず、相続手続きをしなかったからといって、相続人の方に罰則が科されることもありません。
そのため、預金が少額であり、相続手続きの手間暇や、請求するための資料の取得費用を考えると、明らかに割に合わないような場合、例えば、預金は30円しかないが、相続人が被相続人の兄弟であり資料収集に数千円かかるようなケースは、明らかに割に合わないと思われる事例であるため、預金をそのまま放置するということも実際にはあり得ます。
2 預金が少額でも相続手続きを進めたほうがよい場合
金融機関によっては口座管理手数料を要求される場合があるため、そのような費用を避けるために、口座解約の前提で相続手続きを進めるなど、預金が少額でも相続手続きを進めるケースはあります。
また、口座の入出金等の履歴が10年間ないような口座は、休眠口座として取り扱われることがあります。
休眠口座となった場合には、通常よりも手続きが煩雑となるため、休眠口座となる前に、預金が少額でも相続手続きを進めることもあります。
このような、管理手数料の発生や休眠口座となることを避けるために、相続手続きを済ませておくのがよいといえます。
3 預金が少額なら簡易的な手続きが利用できる場合もある
⑴ 預貯金がゆうちょ銀行の場合について
ゆうちょ銀行では、口座残高が100万円以下の場合には、代表相続人を相続人間で選び、その代表相続人が相続人を代表して預貯金の手続きをすることができるという簡易な制度が用意されております。
この手続きにおいては、他の相続人の印鑑は必要なく、代表相続人の印鑑で手続きを進めることができます。
相続人で後日トラブルが生じないように、代表相続人で手続きを進める場合には、事前に他の相続人の同意を取って進めるべきです。
口座残高が100万円を超える場合には、⑶の他の金融機関と同様な手続きが必要となります。
⑵ ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合について
ゆうちょ銀行のような簡易な制度を用意していない金融機関の場合、一般的には以下のような書類が必要となります。
① 各金融機関が用意する相続関係の依頼書類(すべての相続人の署名及び実印の押印)
② 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本
③ 相続人の戸籍謄本
④ 相続人全員の印鑑証明書
しかし相続人間で疎遠な者がいる等の場合にはこれらの書類の収集が困難なことも考えられます。
4 相続手続きは専門家にご相談ください
預金が少額だからといって、必ずしも簡易に相続手続きができるという訳ではありません。
相続人が多い場合には、相続人間の調整や資料収集に時間を要する場合があり手間暇を要し、あるいは、手続きに不備がある場合、ご自身で対応することには困難な場合も予想されます。
そのため、預金が少額であるが、相続手続きをしなければならない場合には、費用対効果の問題もありますが、専門家へのご相談を検討頂くことが望ましいと思います。