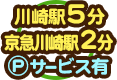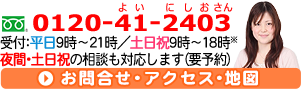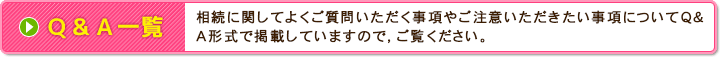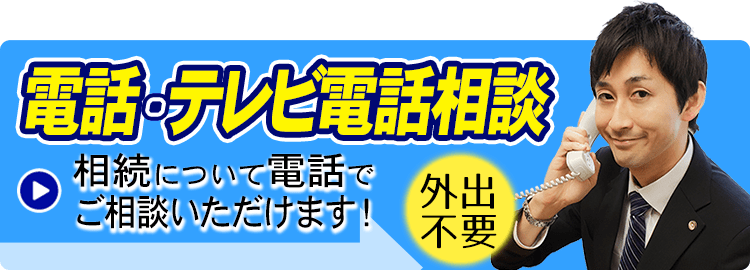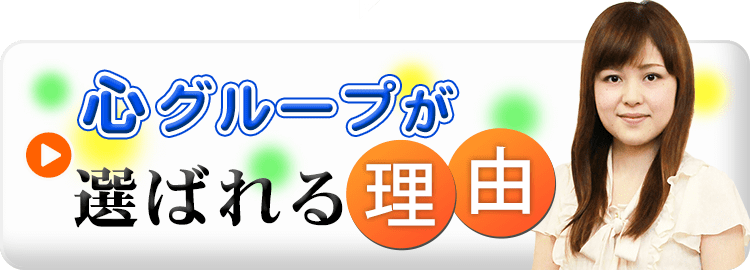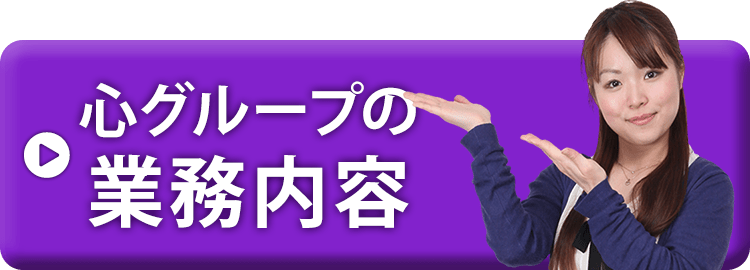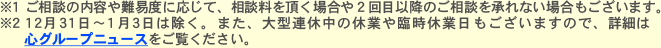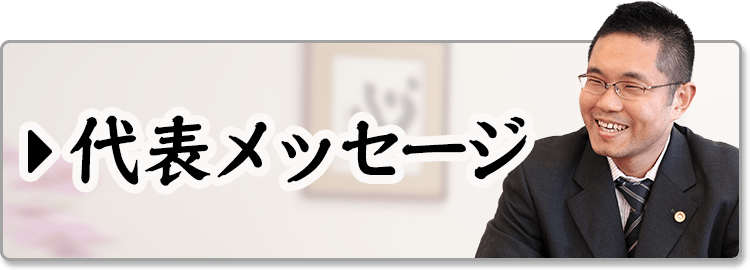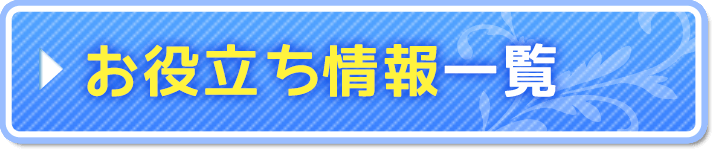不動産の共有名義人が亡くなった場合の相続手続き
1 亡くなった共有名義人の持分も相続の対象となる
不動産の共有名義人が亡くなった場合、亡くなった共有名義人の持分は相続の対象となり、通常の相続手続きと同様に相続人が共有持分を相続します。
その際、令和6年4月から相続登記が義務化されており、相続発生後3年以内に相続登記をする必要があるため、それまでには相続手続きを完了させる必要があります。
2 相続手続きの流れ
⑴ 遺言書の有無を確認する
まずは、亡くなった方が遺言書を残しているかを確認します。
遺言書がある場合は、遺言の内容に基づいて手続きを進めます。
⑵ 相続人を確定する
遺言書がない場合は、亡くなった方の法定相続人(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など)を確定します。
共有持分には法定相続分が適用され、亡くなった共有名義人の持分は、法定相続人に相続されます。
⑶ 相続財産である不動産を調査する
相続財産である不動産を調査し、詳細な状況を把握します。
⑷ 遺産分割協議を行う
相続人全員で遺産分割協議を行い、亡くなった方の不動産の共有持分を誰が取得するか、またはどのように分割するかを話し合います。
話し合いが完了したら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印します。
⑸ 相続登記を行う
遺産分割協議が完了したら、法務局に対し、不動産の共有持分を相続人に移転する相続登記を申請します。
相続登記は相続人全員が共同で、または相続人から委任された第三者が申請することができます。
共有持分の評価額によって、登記費用は異なります。
⑹ 相続税の申告・納付をする
相続財産の評価額に応じて相続税を申告し、納付します。
3 トラブル防止には専門家への相談も
これらの一覧の手続きについて、専門家に相談しながら進めることも検討されるとよいかと思います。
私たちは、相続についてトータルサポートが可能となっていますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。