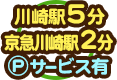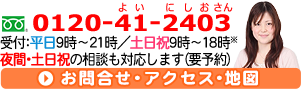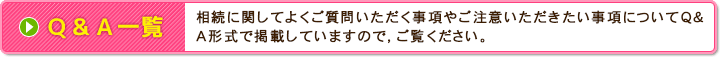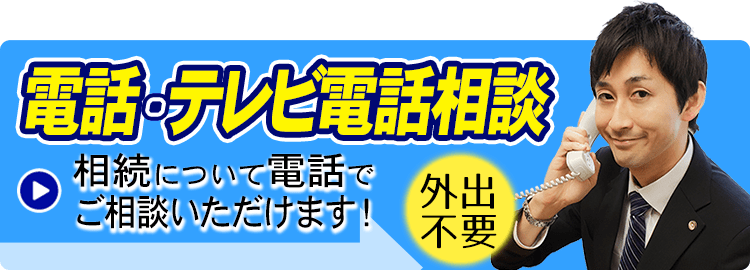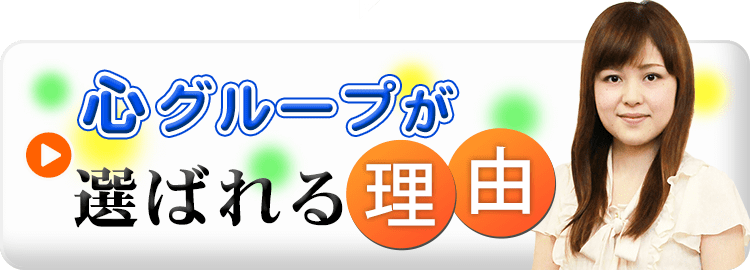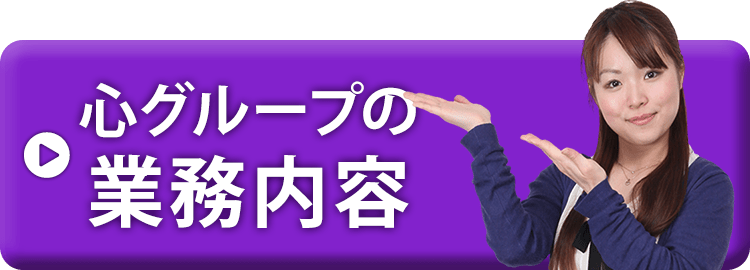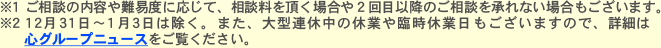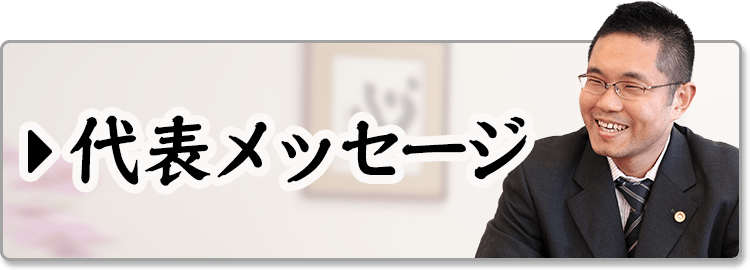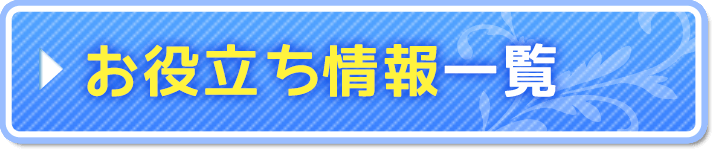寄与分がある場合の遺産分割
1 寄与分がある場合の遺産分割の方法
寄与分がある相続人の相続分は、次の計算で求められます。
【寄与分がある方の相続分の計算式】
(遺産総額-寄与分)×法定相続分+寄与分
被相続人の財産のうち、特定の相続人の寄与によって形成されたといえる分を一旦控除し、あとでその分を寄与した相続人の相続分に加算するという方法です。
ただし、寄与分は相当厳格な要件を満たさないと認められず、立証も簡単ではありません。
また、相続人以外の方が被相続人のお世話をしていた場合などの問題もあります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 寄与分が認められる要件
まず、寄与分を主張できるのは原則として相続人のみです。
相続人でない方が被相続人のお世話をしていたというような場合については3で説明します。
そして、寄与分は、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度の貢献を超えるような貢献(特別の寄与)があったということと、この貢献によって被相続人の財産の増加(財産の減少の抑制も含む)があったということの両方がある場合に認められます。
仕事の合間に家事をしていたとか、施設にお見舞いに行っていたなど、一般的に家族として行われるべき扶養の範囲の行為では、特別の寄与とは認められないと考えられます。
逆に、仕事を辞して、日々介護士の業務と同等の介護をしていたというような場合には寄与分が認められやすいといえます。
また、寄与分の主張には期間制限があることにも注意が必要です。
2023年4月1日以降、寄与分の主張には期間制限が設けられています。
寄与分の主張ができるのは、原則として相続の開始から10年以内となります。
相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときには、10年を経過しても主張可能とされています。
亡くなった人の預金が少額の場合でも相続手続きは必要か 相続放棄で失敗したケース